2025年 最新!NAS用 HDD・SSD ベンチマーク比較|速度・耐久性・コストを徹底検証
yamakashi
ありがとNAS
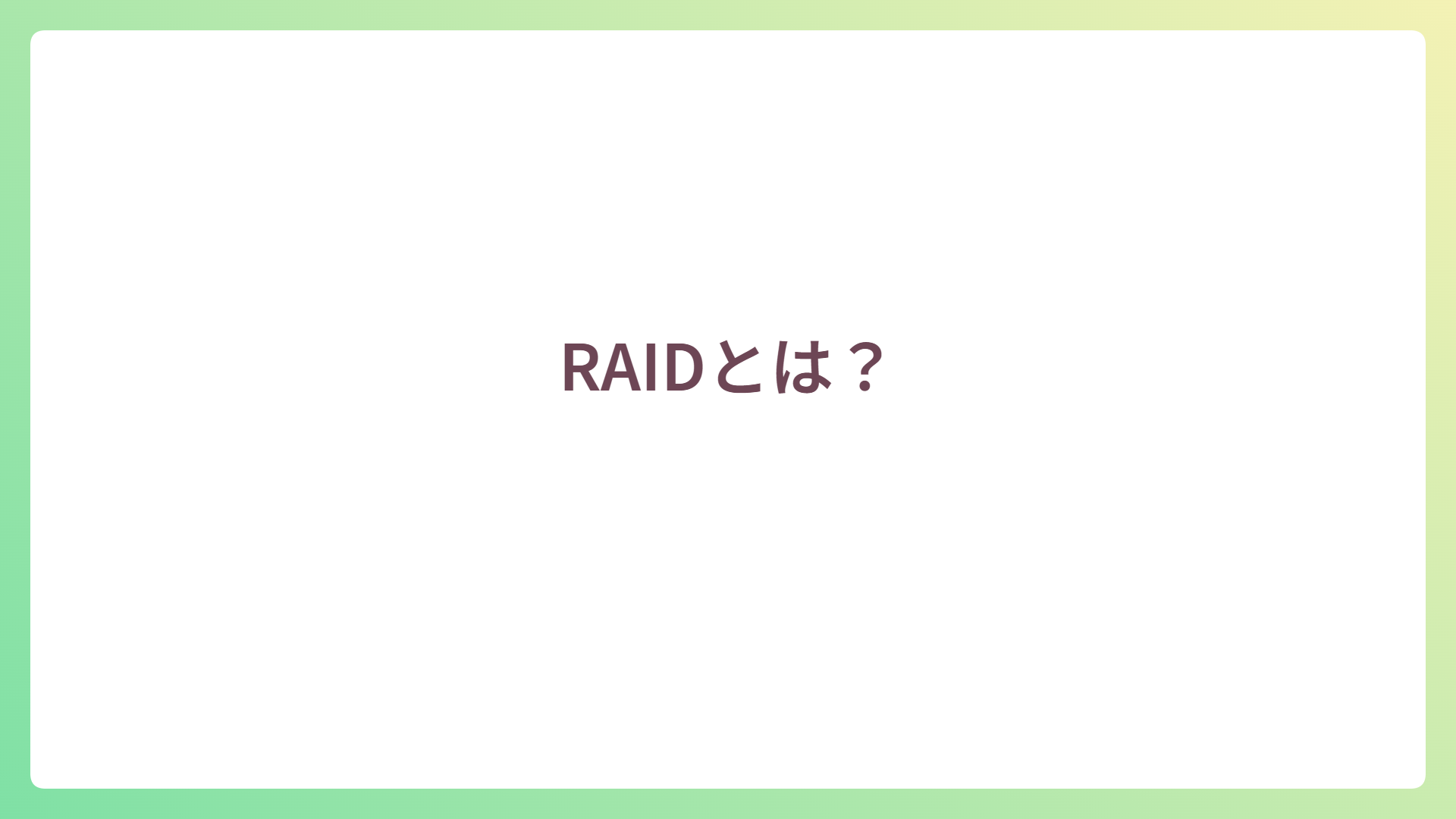
RAID(Redundant Array of Independent Disks:独立ディスクの冗長配列)について、基本から応用まで体系的にまとめて解説します。
RAIDは、複数のHDD/SSDを一体化し、**性能向上やデータ保護(冗長性)**を実現する技術です。主に以下の目的で使用されます:
| RAIDレベル | ディスク数 | 冗長性 | 容量効率 | 読込速度 | 書込速度 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | 2以上 | ❌ 無し | 100% | ◎ 高速 | ◎ 高速 | ストライピング(速度特化) |
| RAID 1 | 2 | ✅ 有り | 50% | ○ やや高速 | △ 遅い | ミラーリング(安全重視) |
| RAID 5 | 3以上 | ✅ 有り | 約67〜94% | ◎ 高速 | △ 遅い(書込時パリティ計算) | パリティ付き分散保存 |
| RAID 6 | 4以上 | ✅ 有り(2台まで故障可) | 約50〜88% | ○ やや高速 | △ 遅い | 二重パリティ |
| RAID 10 | 4以上(偶数) | ✅ 有り | 50% | ◎ 高速 | ◎ 高速 | RAID0+1のハイブリッド |
| JBOD | 1以上 | ❌ 無し | 100% | × 遅い | × 遅い | ただのディスク連結 |
| 分類 | 方法 | 例 |
|---|---|---|
| ソフトウェアRAID | OSや専用ソフトで制御 | Linux mdadm、Windows Storage Spaces、Btrfs |
| ハードウェアRAID | RAIDカードなどの専用機器で制御 | サーバー・高性能NAS |
| ファームウェアRAID(FakeRAID) | マザーボードのRAID機能 | 一部のBIOS/UEFIが対応(信頼性に注意) |
| 用途 | 推奨RAID | 理由 |
|---|---|---|
| 高速処理専用(キャッシュ用途など) | RAID 0 | 速度最優先(データ喪失OK) |
| データ保護が最優先(家庭NAS) | RAID 1 | 構成がシンプル、復旧も簡単 |
| 容量効率と安全性を両立(業務NAS) | RAID 5 | 高信頼・高効率 |
| 高可用性(高額データ/サービス) | RAID 6 または RAID 10 | 2重耐障害・高性能 |
| データより一時保存が目的 | JBOD | 簡単・コスト低 |